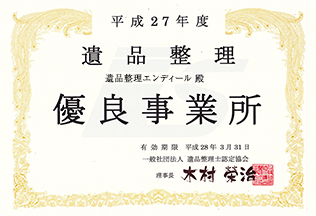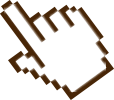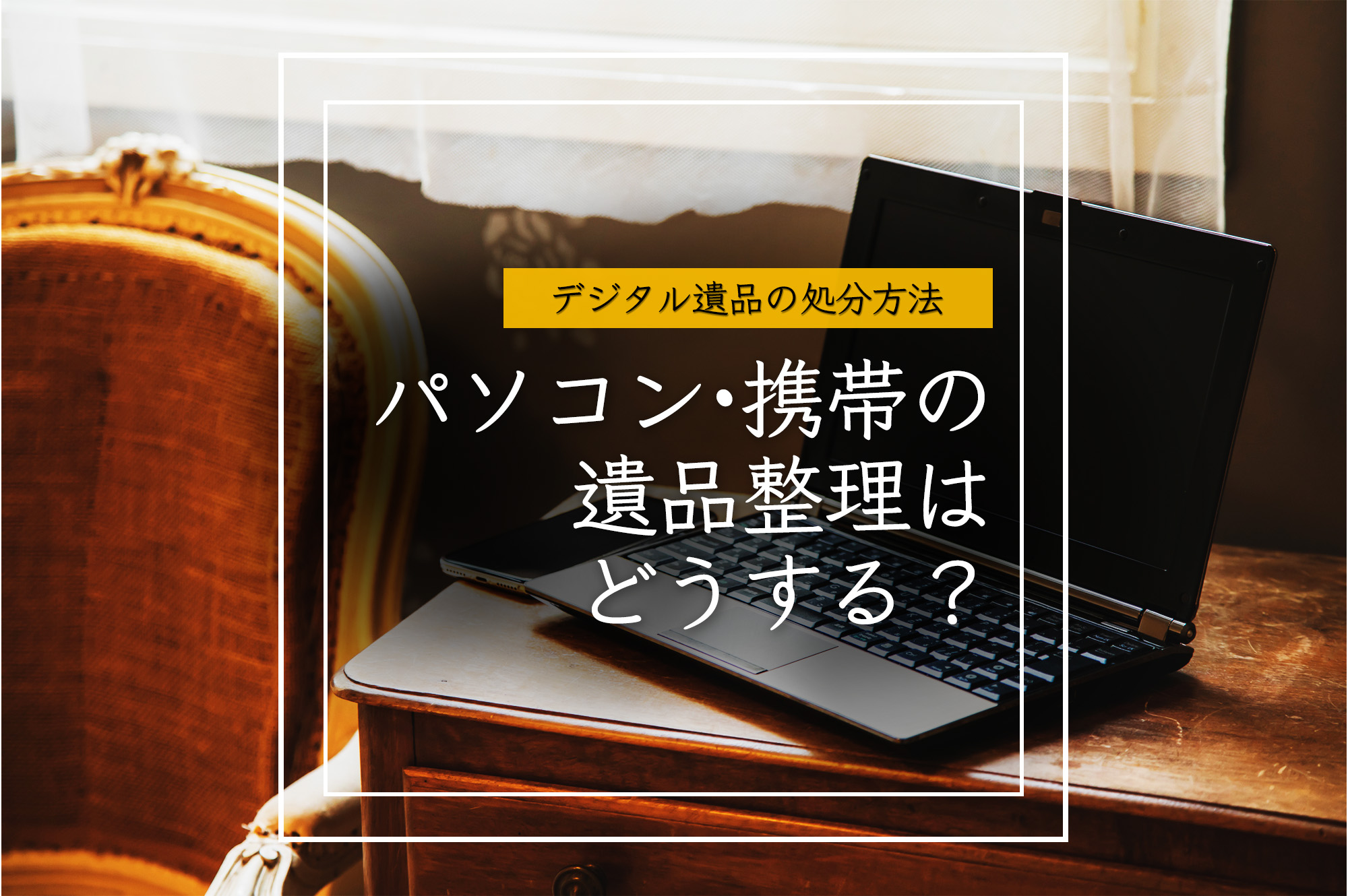
近年、遺品整理の現場で増えているのが「デジタル遺品」の問題です。故人が生前に使用していたパソコンや携帯電話には思い出だけでなく、重要な情報や資産に関わるデータが多く含まれています。
しかし、見た目だけでは中身の重要性を判断しにくく、「古いから捨ててもいいだろう」と安易に処分してしまうと、故人の銀行口座や契約情報が消えてしまったり、個人情報が第三者に漏れたりしてトラブルの原因になることもあります。
この記事では、遺品整理でパソコンや携帯が見つかったときに注意したいポイントや、安全な処分方法について詳しく解説します。
これから遺品整理を控えている方や、すでに作業を進めている方は、ぜひ参考にしてください。
故人のパソコン・携帯は「デジタル遺品」
PCやスマートフォン・タブレットは、単なる電子機器ではなく「デジタル遺品」として慎重に取り扱うべき存在です。
デジタル遺品とは、故人が生前に利用していた電子機器や、その中に保存されたデータ・サービスを指します。たとえば、以下のような情報がデジタル遺品に該当します。
- 写真や動画などの思い出
- 銀行・証券口座の情報やネットバンキングの履歴
- SNSやメール、クラウドサービスのアカウント
- 各種サブスクリプション契約やネットショップのログイン情報
- 仮想通貨やネット証券などの資産情報
これらの情報は、故人のプライバシーや相続に関わるものが多いため、慎重に取り扱わなければなりません。また、誤った処分をしてしまうと「相続できるはずだった資産の消失」や「第三者による情報流出」などのリスクにつながります。
そのため、パソコンやスマートフォンは「ただの不用品」ではなく、「データの中身を確認すべき重要な財産の一部」として扱う必要があります。
遺品整理で出てきたパソコン・携帯を処分するときの注意点
パソコンや携帯電話を処分する際は、後々トラブルにならないよう、いくつか注意点があります。
ここでは、特に注意したい5つの注意点について、詳細を確認していきましょう。
処分方法を遺族で話し合ってから決める
まず、遺品整理で出てきたパソコン・携帯を処分するときは、処分方法を遺族で話し合ってから決めることが大切です。
パソコンや携帯にどのようなデータが残っているかは、外からでは分かりません。写真や手紙のように目に見える遺品とは異なり、デジタル機器の中には、思い出や資産情報などのデータが詰まっている可能性があります。
そのため、処分するかどうか、またどのように取り扱うかは、遺族間でしっかりと話し合い、同意のもとで判断することが大切です。万が一、重要な情報や資産を含んでいた場合、勝手に処分してしまうことで相続トラブルにつながるおそれもあります。
一般ゴミとしては処分できない
パソコンや携帯電話などのデジタル機器は、法律上、一般ゴミとして処分できない点にも注意しましょう。
特にパソコンは「資源有効利用促進法」により、メーカーによる回収やリサイクルが義務付けられており、自治体の粗大ゴミなどでも回収してもらえないことが多いです。
スマートフォンやタブレットは、自治体や家電量販店の回収ボックスでの処分が可能なケースがありますが、事前に確認が必要です。
重要なデータは事前にバックアップしておく
遺品整理で出てきたパソコン・携帯を処分する前に必ず行いたいのが、内部データのバックアップです。一度廃棄してしまうと、たとえデータの存在に気づいても、復元することはほぼ不可能になります。
パソコンであれば、外付けハードディスクやUSBメモリにコピーしておくことで、写真や文書データなどを残すことが可能です。ロックがかかっていて解除できない場合は、パスワード解析やデータ復旧に対応している専門業者に依頼する方法もあります。
スマートフォンは特にプライバシー性が高いため、遺族からの依頼であってもキャリアやメーカーがロック解除を断るケースが多いのが実情です。解除のためには裁判所の許可が必要になる場合もあるため、事前に専門家へ相談しておくと良いでしょう。
データを完全に消去してから処分する
故人が使用していたパソコンや携帯電話を売却・譲渡・廃棄する際は、必ずデータを完全に削除するようにしましょう。
多くの人が行う「ゴミ箱を空にする」「初期化をかける」といった操作だけでは、内部にデータが残ってしまう可能性があります。悪意のある第三者に復元されることで、個人情報が漏えいしたり、トラブルの原因となることもあるので注意が必要です。
安全に処分するためには、ハードディスクを物理的に破壊する、専用のデータ消去ソフトを使う、または信頼できる専門業者に依頼する方法などが有効です。
相続放棄する場合は勝手に処分しない
相続放棄を検討している場合、パソコンやスマートフォンの処分には特に注意が必要です。
相続放棄とは、故人の財産や債務を一切引き継がない手続きです。そのため、放棄するはずの遺品に手をつけてしまうと「財産に関与した」と見なされ、放棄が無効になる(単純承認になる)リスクがあります。
パソコンや携帯電話の中身も「相続財産」と見なされる可能性があるため、相続放棄を予定している人は、自ら処分せず、他の遺族に対応を任せるようにしましょう。
遺品整理で出てきたパソコン・携帯の安全な処分方法

PCやスマホ、タブレットは、データの扱いや法令の関係からも、適切な方法で処分することが求められます。 ここでは、遺品整理で出てきたパソコン・携帯電話の安全な処分方法を5種類ご紹介します。
自治体の指定回収ボックスへの持ち込み
多くの自治体では、小型家電リサイクル法に基づいて、スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器を回収する専用のボックスを設置しています。
市役所や公民館、家電量販店など、利用しやすい施設に設置されていることが多いです。ただし、回収対象は小型家電に限られ、パソコン本体は対象外となっている場合が多いため注意しましょう。
家電量販店への持ち込み
家電量販店では、小型家電のリサイクルサービスを実施している店舗があります。特にスマートフォンやタブレットは、無料回収してくれるケースが多く、利用しやすい選択肢の1つです。
ただし、家電量販店ごとに回収の対象製品や受付条件が異なる場合があるため、事前に公式サイトや電話などで確認しておくことをおすすめします。
また、データの消去は利用者の責任となるため、処分前に忘れずに済ませておきましょう。
メーカーに回収してもらう
不要になったパソコンは、各メーカーが独自に回収・リサイクルの窓口を設けています。
たとえば、富士通やNEC、東芝などの主要メーカーでは、公式サイトから申し込むと輸送伝票や払込書が送付され、自宅から発送して処分できます。
この方法は「資源有効利用促進法」に基づいた正式な処分ルートであり、安全かつ確実に処分したい方に適しています。
また、メーカーが直接受け付けていない場合は、「一般社団法人 パソコン3R推進協会」の回収サービスを利用することも可能です。
参考:
・富士通(FMV) → パソコンリサイクル窓口
・NEC(LAVIE) → 回収・リサイクルページ
・東芝(dynabook) → 使用済みパソコン回収窓口
デジタル機器の宅配回収サービス
最近では、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを宅配で回収してくれる専門サービスも増えています。
自宅にいながら回収してもらえるため、忙しい方や高齢の方にとっては大変便利です。また、回収だけでなく、データの完全消去やリサイクル証明書の発行に対応している業者もあり、安全性の面でも安心できます。
処分とあわせてデータ消去を確実にしたい方には、こうしたサービスの利用を検討してみると良いでしょう。
遺品整理業者への依頼
遺品整理と一緒にパソコンや携帯の処分を進めたい場合は、遺品整理の専門業者に相談するのも有効な選択肢です。
デジタル遺品の扱いに慣れた業者であれば、必要に応じて専門業者と連携し、安全なデータ消去や処分を代行してくれます。
特に、他の遺品も大量にある場合や、デジタル機器の扱いに不安がある場合は、仕分けから処分までを一括で依頼できる遺品整理業者のサポートが心強いでしょう。
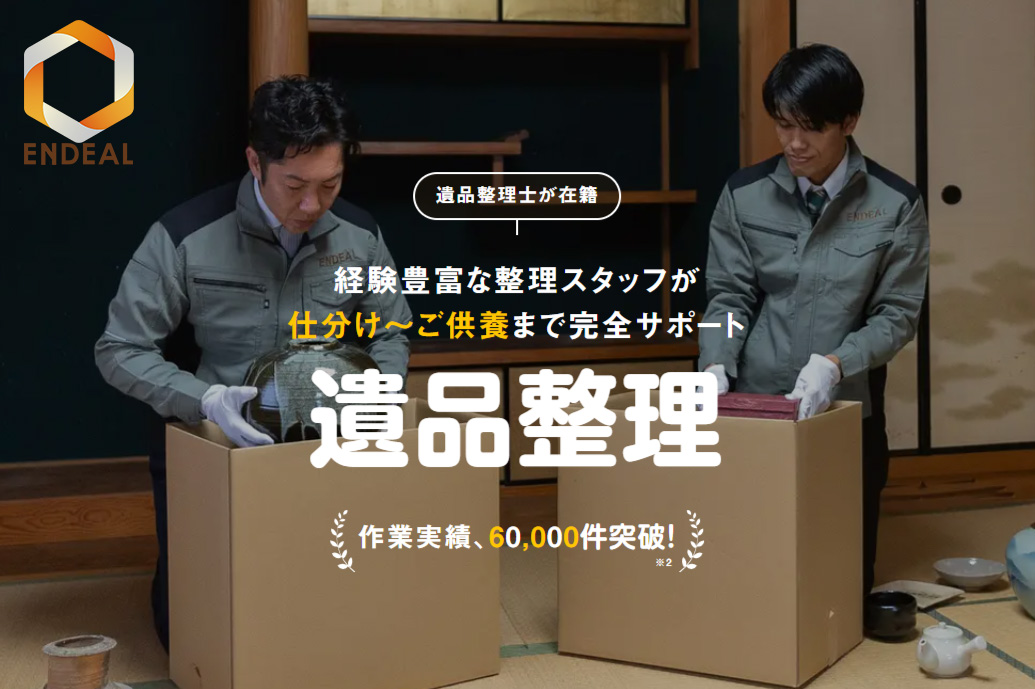
遺品整理は、私たちエンディールにぜひお任せください。
エンディールでは迅速・丁寧・真心をモットーに、年間施工件数900件を超える遺品整理を実施しております。
遺品整理士の有資格者が在籍する優良事業所として認定されており、遺品のご供養や買取、家屋の解体、不動産買取などのオプションサービスもご用意しております。
お見積りは電話・出張ともに無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。
通話無料!専門スタッフが丁寧に対応
CONTACT US
-
通話無料、秘密厳守!
0120-77-2345
受付時間8:00~20:00(年中無休)
-
入力、約3分で完了!
メールで無料お見積り無料ご相談
-
LINEでご相談!
LINEでお気軽にご相談・質問
まとめ
今回は、遺品整理で出てきたパソコンや携帯電話の処分するときの注意点や、安全な処分方法について、詳しく確認してきました。
パソコンや携帯電話などのデジタル機器には、個人情報や資産情報が含まれていることが多く、慎重な取り扱いが必要です。事前にバックアップを取ったり、データを完全に消去したりしたうえで、法令に沿った方法での処分が重要になります。 今回の内容を参考にして、安全かつ適切な方法でデジタル遺品を取り扱い、後悔のない遺品整理を実現させましょう。